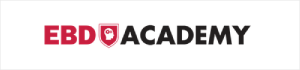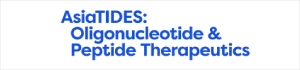過去の記事一覧
メルマガ登録
毎月5日、15日、25日の3回に渡り、製薬業界の注目ニュースを
Eメールにてお届けいたします。
※※配信日が土日祝の場合は翌営業日の配信となります。
運営会社

<広告掲載など各種お問い合わせ先>
UBMジャパン株式会社
東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル2F
TEL:03-5296-1020
Email: pharma-navi@cphijapan.com
Copyright © UBM Japan Co., Ltd. All rights reserved.