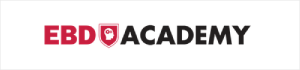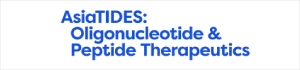最近のFDAの生物製剤市場における競争とイノベーションに関する公聴会で、これらおよびその他の著名な規制、法律、研究の問題は、イノベーター企業やバイオシミラーメーカーの代表者、患者支持者、プロバイダーによって取り上げられました。
FDAは2018年9月21日までに、バイオシミラーの行動計画をさらに進展させ、利害関係者からより広範な正式なコメントを得ることを期待している。
バイオシミラーメーカーは、欧州やその他の先進国で承認された同様の製品の臨床試験データを提出する余裕を求めており、数多くの患者支持者が、潜在的なコスト削減を上回る生産安全性と同等性の重要性を強調し、革新者の立場を支持した。
また、バイオシミラー対ブランドの明確な名称とラベル付けの必要性は、有害事象や市販後の開発を追跡する際の混乱を避けるために重要なものとして、イノベーターや患者グループによって支持されました。
新たな問題としては、患者をバイオシミラーに切り替えると追加の費用が発生する可能性があるというブランドの主張です。 AbbVieによって資金提供された最近の研究では、自己免疫状態の患者を同様の療法に移行させることが安全で適切であることを確認するために、検査や医師の診察に高い支出があることが記載されています。
詳細はこちら【英語】
http://www.pharmtech.com/biosimilars-battles-heat-0
<PharmaTech.com 2018.9.10>